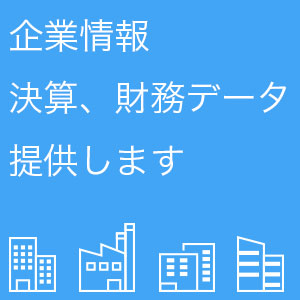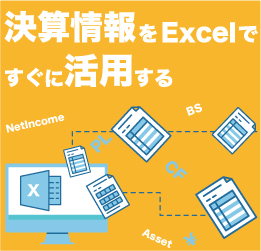非鉄金属 <5803> 株式会社フジクラ 課題
課題
1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
(1) 経営方針
当社は、創立120周年に当たる2005年度を「第3の創業」の年と位置づけ、経営理念である「ミッション・ビジョン・基本的価値」を指針とし、“つなぐ”テクノロジーを通じて「顧客価値創造型」事業へ積極的に展開し、収益性重視のスピード感ある積極経営で豊かな社会づくりに貢献してゆく所存であります。
(2) 経営環境
経済環境としては、波状的な新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大が生じ、世界中の社会経済活動が大きく制限される状況が継続する中、ロシアによるウクライナ侵攻等の地政学リスクの高まり、米国を中心としてインフレ懸念もあり、世界経済等の不確実性に留意が必要な経済環境となっております。
エネルギー・情報通信分野においては、国内はインフラの成熟化により、大きな需要の伸びが見込めない状況にあります。また、海外については情報通信分野において、リモート化・クラウド化の進展によるFTTx、データセンタ投資が欧米を中心に今後も需要拡大が見込める状況が継続する見通しですが、原材料価格の高騰、安定調達については注意が必要な状況です。
エレクトロニクス分野においては、当社FPC(フレキシブルプリント配線板)、コネクタが多く使用されている主要顧客のスマートフォンの需要は堅調に推移するとともに、巣ごもり需要の継続、設備投資の拡大による産業機械向け部品需要の高まりがみられる状況ですが、中国上海地区を中心とした新型コロナウイルス感染症の拡大等、外部環境について注意が必要な状況です。
自動車分野においては、世界の自動車生産台数については新型コロナウイルス感染症の拡大・半導体不足に伴う受注・生産に対する不安定感がみられますが、CASE(Connectivity:コネクテッド、Autonomous:自動運転、Shared & Service:シェアリング&サービス、Electric:電動化)が主要なテーマとなるなど、自動車は100年に一度の革新期にあり、新エネルギー車の需要拡大、自動車の電子化・情報化が一層進展するものと見込まれます。
(3) 対処すべき課題
①「事業再生フェーズ」から「持続的成長フェーズ」への戦略転換
当社は「事業再生フェーズ」とした2020年度以降、事業再生計画「100日プラン」に基づき、「グループガバナンスの強化」及び「既存事業の聖域なき『選択と集中』」を重点施策として、全社一丸となって早期事業回復に向け痛みを伴う構造改革を含む多くの施策を断行してまいりました。2022年2月に公表いたしました「FPC事業の分社化」、及び「エネルギー事業の分社化」にかかる方針決定をもって、当社事業の再生に向けた一連の取り組みに目途がついたものと判断し、持続的成長フェーズへ舵を切ることを決断したものです。
2022年度はフェーズ転換を確実にするため、組織再編を着実に進める一方、2023年を開始年度とする中期事業計画を本事業年度中に策定、持続的成長を通じて企業価値向上を図ることができる企業体を目指します。尚、中期事業計画の公表は2023年5月を予定しております。
②新たな経営体制
新たな成長に向けて踏み出した「新生フジクラ」の経営体制として、CEO(最高経営責任者、Chief Executive Officer)に加えてCFO(最高財務責任者、Chief Financial Officer)及びCTO(最高技術責任者、Chief Technology Officer)を設置いたしました。これは、持続的成長の実現に向けて、経営の機能強化、意思決定の迅速化を図るためのものです。
「事業再生フェーズ」下では、CEOとCOOに権限を集約して、構造改革と中核事業の安定化を推進してきました。2022年度より「持続的成長フェーズ」に踏み出すにあたり、「モノづくりの会社」である当社にとって、高い技術力を背景とした戦略の策定と、これを支える財務基盤の確立が重要であると考えています。特に技術及び財務の分野では、高い専門性と豊富な経験を有するとともに、全社的な視座をもって戦略の策定や業務を遂行できる人財を登用することが必須となります。CFOとCTOが財務面と技術開発面の専門性を活かした機能をもってCEOの機能を支援又は補完することにより、CEOが全社戦略の推進を遺憾なく発揮できる体制としました。また、海外事業比率の高い当社の最適な経営体制として、全社戦略(CEO)、財務(CFO)、技術(CTO)に加え、グローバルの機能を加えることによって、企業価値の向上及び持続的成長を図ってまいります。
一方、取締役会の監督機能の強化として、本年4月に業務執行を担わない取締役会長が取締役会の議長となることで、取締役会の議事運営の公正性・公平性を高めることとしました。
加えて、本年定時株主総会にてご提案する新たな経営体制では、取締役総数11名のうち4名を業務執行取締役、7名を業務執行を担わず経営の監督を行う取締役(業務執行を担わない取締役会長1名及び監査等委員である取締役6名)としています。
③2022年度の経営計画と事業部門ごとの重点課題
2022年度の連結の事業計画は、売上高7,000億円(前年度比4.4%増)、営業利益420億円(同9.7%増)、経常利益370億円(同8.5%増)、親会社株主に帰属する当期純利益は225億円(同42.5%減)としました。
[エネルギー・情報通信事業部門]
エネルギー分野では、これまで主として新興国の電力インフラ構築による社会貢献に携わってきた海外生産拠点はその役割を終え、2020年度をもって全拠点から実質的に撤退しました。あわせて、海外EPC事業(*)からの撤退、および国内事業の選択と集中を実施してまいりました。2022年度は、2022年2月に公表いたしましたエネルギー事業の分社化を確実に進め、エネルギー事業の安定化を図ります。
*)「EPC事業」とは、電線・ケーブルの供給並びに敷設工事の設計及び施工を一体として提供する事業を言います。(Engineering:設計、Procurement:調達、Construction:建設)
情報通信分野では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴うテレワーク需要の高まり、5G、IoT等の次世代インフラ整備の需要と相まって、特に欧米を中心としたFTTx、データセンタ等の通信インフラ網構築への積極的な投資が引き続き見込まれます。当社の戦略商品SWR®/WTC®は、細径・軽量・高密度、加えて敷設工事における簡便性という特長から通信インフラ増強に最適なソリューションであるとの高評価を得ています。こうした機会を逃すことなく更なる製造能力の増強等、リソースの集中を図り、周辺部品等を加えた光インフラ網構築に向けたトータルソリューションの提供を行ってまいります。
[電子電装・コネクタ事業部門]
FPC事業では、2022年2月に公表しました通り、この事業の再生及び安定化を期すため、2022年5月に当社100%子会社である株式会社フジクラプリントサーキットに集約、ひとつの事業体としました。かかる組織再編及び事業の安定的な移管を確実に進めるとともに、従来からの取り組みである品質の向上・技術力の強化についても一層磨きをかけ、競争優位性の維持できる領域へと事業をシフトしてまいります。
コネクタ事業では、これまで進めてきた構造改革を通じた生産体制の最適化により、安定した事業運営がなされるようになりました。今後、新しい市場分野への参入を通じた持続的成長を求めてまいります。
電子部品事業では、拡大するデータセンタ需要に対し、HDDの大容量化への対応、熱ソリューションの提供など、新規市場の開拓や新規顧客を取り込む等新陳代謝を促進し、高収益性を維持してまいります。
自動車事業では、新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響及びウクライナ・ロシア問題を契機としたサプライチェーンの上流及び下流双方における原材料調達や価格の安定性にかかる懸念があり、インフレ問題等、自動車業界は先行き不透明となっています。一方、当社事業としては、これまで取り組んできた構造改革の推進等により「稼ぐ力」は戻ってきていると判断しています。引き続き、各拠点のさらなる生産性の向上と品質の安定化によるコスト削減をすすめてまいります。
エレクトロニクス関連事業全体に関する今後の取組として、エレクトロニクス製品の自動車市場への導入を進めています。自動車業界は「CASE」(コネクテッド、自動運転、シェアリング、電動化)などの100年に一度の変革期を迎えています。当社では既に複数のお客様と高速通信対応、電力制御システム等の共同開発を進めており、またコネクタ事業部門では次世代車両間通信用コネクタを2021年度から量産開始したほか、FPC事業においても従来から手掛けるインフォテイメント(*1)やライティング(*2)分野に加え、パワートレイン(*3)分野の製品開発を加速させてまいります。
(*1)「インフォテイメント」とは、インフォメーション(情報)とエンターテイメント(娯楽)を組み合わせた造語であり、特に自動車分野におけるナビゲーションシステムやオーディオビジュアル機器向け製品を指します。
(*2)「ライティング」とは、ヘッドライト、方向指示器、室内照明等の自動車用照明を指しています。
(*3)「パワートレイン」とは、動力伝達装置全般のことを指しており、自動車の挙動としての「走る」「曲がる」「止まる」といった動きを介する装置に使用される電子部品を指しています。
[その他(新事業創生・研究開発部門)]
再生フェーズにおいても常に事業や製品・技術の新陳代謝を探索し、研究・開発を続けることは企業にとって必須の事項であり、再生を果たした後の持続的成長に向けた取り組みを進めていくためにもこれを継続しなければなりません。そのため、これまで設置していた新規事業推進機能とR&D機能を統合し、2021年4月に「新事業創生・研究開発部門」を新たに設置いたしました。
これは、以下の3つを目的としたものです。
・既存事業を支える技術を世界トップレベルに維持し、革新的な新商品を創出すること
・新たな立地の検討・技術基盤の構築・事業化まで一気通貫で推進すること
・技術的な見地からフジクラの未来のあるべき姿を見定め、成長戦略の構築に貢献すること
当社としましては、新たな価値創出を目指し、市場ニーズや需要の動向などを見極めながら、当社のコア事業・技術を活かせる重点テーマに絞り込んで、新規事業の創出、新製品の開発を継続してまいります。
④TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)に沿った気候変動関連情報開示
フジクラグループは、1992年に制定した「フジクラグループ地球環境憲章」に始まり、外部研究機関の予測などを参考に、経営戦略と一体となった環境活動方針を定めています。2016年にはIPCC(気候変動に関する政府間パネル) RCP2.6*(2℃シナリオ)によるシナリオ分析を行い、フジクラグループ環境長期ビジョン2050を制定しました。2050年の未来を見据え、環境負荷の最小化に向けた4つのチャレンジに取り組んでいます。
フジクラグループ環境長期ビジョン2050で掲げる4つのチャレンジ
※経営計画に影響を与える可能性が高い気候変動リスク
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有(被保有分)を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。