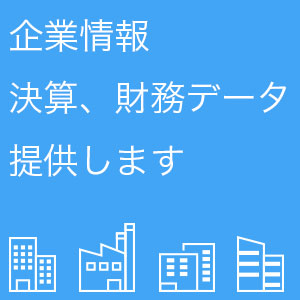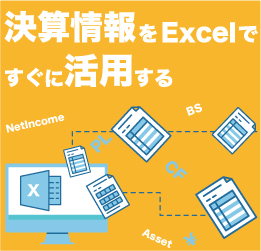保険業 <7181> 株式会社かんぽ生命保険 課題
課題
1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
文中の将来に関する事項は、別段の記載がない限り、本書提出日現在において当社グループが判断したものであります。
(1) 経営方針
当社が掲げる経営理念には、お客さまによりそい、一人ひとりの人生を守り続けていくために、全社員一丸となって歩んでいくという、当社の決意が込められております。この経営理念を実現するため、当社が目指していく具体的な姿を経営方針として制定しております。
(経営理念)
いつでもそばにいる。どこにいても支える。すべての人生を、守り続けたい。
(経営方針)
かんぽ生命保険は、お客さまから選ばれる真に日本一の保険会社を目指します。
① お客さま一人ひとりの人生によりそい、分かりやすい商品と質の高いサービスを提供します。
② お客さまにより良いサービスを提供するため、お客さまと接する社員が力を発揮する態勢を整備します。
③ 社員一人ひとりが成長でき、明るく生き生きと活躍できる環境をつくります。
④ コーポレート・ガバナンスの確立による健全な経営を行い、常に新しい価値を創造することで、持続的な成長を生み出します。
⑤ 健康促進、環境保護、地域と社会の発展に積極的に貢献します。
⑥ すべてのステークホルダーと密接なコミュニケーションを図ります。
(2) 経営環境
2021年度の日本経済は、経済活動の再開が徐々に進む中、各種政策効果や海外経済の改善もあり回復基調となったものの、新型コロナウイルス感染症の感染再拡大が断続的に発生する中で、その動きは緩やかでした。米国経済は、供給制約の問題や物価上昇が下押し要因となったものの、内需を中心に堅調な回復が続きました。欧州経済は、年度前半は個人消費を中心に堅調に推移したものの、年度後半は新型コロナウイルス感染症の感染再拡大や物価上昇等の悪影響から回復は鈍化しました。
こうした経済状況の中、運用環境は以下のようになりました。
国内長期金利は、日本銀行による長短金利操作付き金融緩和政策の下、概ね0%~0.1%程度で推移していましたが、米国における利上げの開始等を受けて海外金利が急上昇する中、年度末にかけて上昇し、3月末は0.21%程度となりました。
日経平均株価は、国内で新型コロナウイルス感染症の感染再拡大が発生する中、年度始から緩やかな低下基調で推移しました。9月には、国内新政権への期待感の高まりや、新規感染者数の減少等を受けて30,000円を超える水準まで上昇しましたが、オミクロン株による感染再拡大等を受けて再び低下基調となり、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻等もあって3月上旬には24,000円台まで下落しました。その後は、米国株式市場の反発や円安の進行が好感されたことで上昇し、3月末は27,000円台となりました。
また、近年、生命保険業界を取り巻く経営環境は大きく変化しております。
少子高齢化の進展や単身世帯の増加に伴い伝統的な死亡保障へのニーズが縮小する一方、社会保障制度に対する不安感や自助努力意識の高まりから、医療・介護等の第三分野商品に対するニーズの拡大が見られ、今後もこの傾向は継続するものと考えられます。さらに、新型コロナウイルス感染症が大きな影響を及ぼし続けており、お客さまに迅速かつ適切に保険金等をお支払いするという生命保険事業の社会的役割は重要性を増しております。また、各種サービスのデジタル化に向けた取り組み等が進展しており、当社としても、時代とともに加速するお客さまの価値観やライフスタイルの変化・多様化に合わせて最適なサービスを提供できるよう、引き続きお客さま本位の業務運営の推進・定着に取り組んでいます。
販売チャネルにつきましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う環境変化等により、従来からの営業職員チャネルや銀行を中心とした金融機関の窓口販売チャネル等の対面チャネルに加え、デジタル技術の活用により非対面・非接触での保険サービスを提供する取り組みが進んでおります。
当社におきましては、創業以来、養老保険・終身保険を中心とした簡易で小口な商品を、全国津々浦々の郵便局を通じて、家庭市場を中心に多くのお客さまにご提供するという独自のビジネスモデルを展開してまいりました。商品・チャネル・顧客基盤といったこれらの特徴は、他社にはない当社の大きな強みである一方、時代や環境の変化に適応したビジネスモデルの転換を図る必要性を認識しております。かかる課題認識を踏まえた当社の成長戦略の詳細は、下記「(4) 経営戦略及び対処すべき課題」に記載のとおりであります。
また、当社は、2019年度において、お客さまのご意向に沿わず不利益が生じた契約乗換等に係る事案及び法令違反又は社内ルール違反が認められた事案が判明いたしました。これにより、2019年12月27日に金融庁から、保険業法第132条第1項に基づく業務停止命令(2020年1月1日から3月31日まで)及び業務改善命令を受け、2020年1月31日に業務改善計画を金融庁に提出し、その後定期的に進捗状況を報告しております。
当該業務改善計画の実施状況及び2021年4月より移行した新たな営業スタイルについては、下記「(4) 経営戦略及び対処すべき課題」に記載のとおりであります(以下、かかる事案の経緯及び再発防止に向けた取り組み等を総称し、「募集品質に係る諸問題」といいます。)。
(3) 目標とする経営指標
当社は、お客さまから真に信頼される企業へと「再生」し、お客さまに「かんぽ生命に入っていてよかった」と感動いただけるよう、お客さま体験価値(CX)※1を最優先とするビジネスモデルへ転換することで、「持続的成長」を目指す、との経営の方向性を示すものとして、2022年3月期からの中期経営計画を、2021年5月に公表いたしました。本中期経営計画において、当社グループは、お客さまのご評価を主要目標として設定し、「お客さま満足度」※2や「ネットプロモータースコア(NPS®)」※3の向上を目指してまいります。また、ご契約の継続を重視し、経営基盤を維持していくためのストックベースの目標として「保有契約件数(個人保険)」を設定するとともに、財務目標として「連結当期純利益」、「1株当たり配当額」及び「EV成長率」を設定しております。
※1 お客さま体験価値(CX)とは、Customer Experienceの略語で、商品やサービスの価格や性能といった機能的な価値だけではなく、保険加入前から加入後のアフターフォロー、保険金支払までのプロセスすべてを通じてもたらされる満足感などの感情的・心理的な価値も含めた、お客さまが体験されるすべての価値のことです。
※2 お客さま満足度を5段階評価として、「満足」「やや満足」として回答いただいた合計割合です。
※3 ネットプロモータースコア(NPS®)とは、Net Promoter Scoreの略語であり、ベイン・アンド・カンパニー、フレッド・ライクヘルド、サトメトリックス・システムズの登録商標です。
当該主要目標の達成状況については、下記「3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (3) 目標とする経営指標の達成状況等」に記載のとおりであります。
(4) 経営戦略及び対処すべき課題
(当社における募集品質に係る諸問題について)
当社は、上記「(2) 経営環境」に記載のとおり、2019年度において発生した募集品質に係る諸問題に関し、2020年1月31日に業務改善計画を金融庁に提出し、その後定期的に進捗状況を報告しております。当該業務改善計画に掲げた再発防止策(健全な組織風土の醸成・適正な営業推進態勢の確立、適正な募集管理態勢の強化及び取締役会等によるガバナンスの強化)については、その大部分は既に実施済みとなっており、2021年12月には、JP改革実行委員会※1(2020年4月から2022年3月まで設置)より、業務改善計画については概ね計画どおり順調に進捗している旨の評価を得ております。
当社は、募集品質に係る諸問題の反省を踏まえ、2021年4月より、営業活動を通じたお客さまとの信頼関係の構築を進めていく新たな営業スタイルへ移行しております。具体的には、「お客さまにご納得・ご満足いただいた上で保険サービスをご利用いただく」活動を徹底していく中で、商品を前提にしたご提案ありきの旧来のスタイルから、適切な募集プロセスの下、勧誘方針※2やかんぽ営業スタンダード※3などのプリンシプルに基づく新たなスタイルへ抜本的に転換しております。
また、お客さまとの信頼関係を構築し、保険会社としての使命を果たしていくためには、かんぽ営業に携わる社員一人ひとりが、安心感や納得感を持って営業活動・お客さまへのご提案を推進していく必要があることから、2021年9月に「かんぽ生命の約束」を策定しております。当該約束では、かんぽ営業に携わるすべての社員に対して、「お客さま本位の営業活動・適正な募集を行っている社員を守る」、「フロントラインの社員一人ひとりに寄り添う」、「お客さまニーズに即した商品・サービスを提供するとともに、適正な営業活動を推進する」ことを、かんぽ営業に係る基本的な考え方・スタンスとして掲げており、当社では、これを遵守・実行してまいります。
※1 日本郵政グループに対する国民の皆さまからの信頼回復に向けて、外部専門家の方々に公正・中立な立場から各種アドバイスをいただくことを目的として設置しておりました。
※2 勧誘方針とは、生命保険の使命等を踏まえた高い倫理観に基づき保障を提供するという、プリンシプルベースのお客さま本位の理念に基づく方針です。
※3 かんぽ営業スタンダードとは、勧誘方針に基づく真のお客さま本位の営業活動の実践に向けた行動原則です。
(中期経営計画)
当社は、2021年5月に中期経営計画を公表しており、お客さまから真に信頼される企業へと再生し、お客さまに感動いただける保険サービスのご提供を通じて、持続的な成長を目指してまいります。
① 再生に向けた取り組み
ア.信頼回復に向けた取り組みの継続
2022年4月より、専門性と幅広さを兼ね備えた新しいかんぽ営業体制を構築し、日本郵政グループ一体での総合的なコンサルティングサービスを実施してまいります。
リテール領域では、当社内にかんぽサービス部を新設し、日本郵便株式会社から同部に出向したコンサルタント(主にお客さまのお宅を訪問して活動する社員)は、当社商品及びがん保険商品のご提案・アフターフォローに専念するとともに、当社が直接責任をもってマネジメントする体制とします。加えて、お客さま担当制を導入することで、お客さまのライフステージの変化等によるニーズの変化に適切に対応するための定期的なコンタクトを充実させ、お客さまに寄り添った質の高いアフターフォローを実施してまいります。
これらの施策を実施するにあたり、2022年3月に、「かんぽ営業(リテール領域)の目指す世界観」を定めております。ここでは「お客さまの信頼・満足を起点としてお客さま数を拡大していく」、「フロントラインに寄り添った仕組み・制度の運用を通じ、適正なマネジメントを定着させ、社員の成長を支える」及び「社会・経営環境を敏感に捉え、進化し続ける」ことを掲げており、この世界観を全社員で共有し、実行していくことで「マーケットも人材も成長させる文化」への転換を図ってまいります。その実現に向けては、土台であるマネジメントの成長を促すために、全社一体となってフロントラインのマネジメントに寄り添い、フロントラインの課題の解決に取り組んでまいります。また、営業目標、評価、手当等の諸制度について世界観と同期を図った形へ大きく見直し、2022年度の営業目標については、新契約と契約継続の両面を評価する保有契約の純増を観点とした目標を導入するとともに、アフターフォローや募集品質の維持などの活動を評価する目標をバランスよく設定し、結果に至るまでのプロセスも重視してまいります。これらの制度の仕組み・運用については、お客さまのためにできることを最優先に考えるとともに、変化し続ける社会環境や経営環境に適切に対応しながら、不断の見直しを図ってまいります。
法人営業領域でも同様に、2020年度に定めた法人営業ビジョン「社員一人ひとりがお客さまや地域社会とともに進化することに挑戦し続けます」に基づき、引き続き、経営者に寄り添い、より幅広く、より質の高いサービスをご意向に合わせてご提供することにより、お客さまとの真の信頼関係を構築、拡大してまいります。
イ.事業基盤の強化
a.保険サービスの充実
当社では人生100年時代における、あらゆる世代のお客さまの保障ニーズにお応えする保険サービスの開発を進めてまいります。
昨今、医療の進展により入院日数は短期化傾向にあるとともに、外来での手術も定着しております。他方で、病気によっては長期の入院が必要となり、経済的に不安を抱えているお客さまも多く、公的医療保険制度の対象外となる費用負担などに対応した医療保障へのニーズは高いと考えております。このようなニーズに対応するため、2022年4月より、新しい医療特約「もっとその日からプラス」の取扱いを開始しております。「もっとその日からプラス」では、従来の医療特約より、入院一時金の金額・回数を充実させ、短期・長期のいずれの入院にも対応するとともに、外来又は入院中の手術のどちらでも同じ手術保険金額をお受け取りいただける、手厚い医療保障をご提供しております。
このほか、2022年4月より、お客さまの利便性向上を図るため、生命保険商品の受託販売範囲を広げるとともに、法人向け商品の受託販売等について、経営者向け定期保険に付加できる特約の種類を拡大しております。
今後も、青壮年層のお客さまニーズに応える低廉な保険料でバランスのとれた保障の提供や、人生100年時代を踏まえた高齢・中高年層の保障等のニーズに応える商品の拡充のほか、お客さまの健康づくりをサポートする商品の研究に取り組んでまいります。
b.資産運用の深化・高度化
資産運用においては、ERM※1のフレームワークの下、ALM※2運用を基本として、安定的な資産運用収益の確保を目指すとともに、2025年予定の経済価値ベースの新資本規制導入の動きに適切に対処しつつ、オルタナティブ等の投資領域ごととポートフォリオ構築の両面から資産運用を深化・高度化してまいります。
収益追求資産への投資については、中期経営計画期間(2021~2025年度)において、総資産に占める同資産の比率を18~20%程度まで引き上げることを見込んでおります。特にオルタナティブ投資※3については、プライベートエクイティ、不動産ファンド、インフラエクイティ、ヘッジファンドの4分野で戦略分散・地域分散を図りながら、リスク許容量と投資機会に応じて段階的に投資残高を積み上げてまいります。
ESG※4投資については、温室効果ガス削減目標達成に向けた投資先に対するエンゲージメントの強化、中期経営計画期間中のKPIに設定した、投融資先再生可能エネルギー施設の総発電出力※5の目標達成に向けた投融資の積極化、社会課題解決に向けたインパクト投資※6の推進を進めてまいります。
※1 ERMとは、Enterprise Risk Managementの略語で、会社が直面するリスクに関して、潜在的に重要なリスクを含めて総体的に捉え、会社全体の自己資本などと比較・対照することによって、事業全体として行うリスク管理のことです。
※2 ALMとは、Asset Liability Managementの略語で、資産負債の総合管理のことです。
※3 オルタナティブ投資とは、債券や上場株式などの相対的に歴史の長い金融商品(伝統的資産)以外の新しい投資対象や投資手法の総称です。
※4 ESGとは、環境(Environment)・社会(Social)・ガバナンス(Governance)の頭文字を合わせた言葉です。
※5 投融資先再生可能エネルギー施設から出力される電力に限ります。当社持ち分換算後です。
※6 インパクト投資とは、財務的リターンと並行して、ポジティブで測定可能な社会的及び環境的インパクトを同時に生み出すことを意図する投資行動を指します。
c.事業運営の効率化・高度化
デジタル化の推進により、お客さまサービス向上と業務の効率化及び経費の削減に取り組んでいくほか、さらなる事業費管理の高度化に向け、自律的にコストコントロールの役割を担う予算管理者を本社各部に設置する等の新たな事業費管理の仕組みを導入し、経費削減を進めてまいります。これにより生じた経営資源は、お客さまサポート領域、DX(デジタルトランスフォーメーション)※の推進等の強化領域にシフトしてまいります。
※ DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立することをいいます。
② 持続的成長に向けた取り組み
ア.お客さま体験価値の向上
お客さま体験価値(CX)の向上の観点から、保険サービスを抜本的に見直し、お客さまの利便性や募集品質を向上させることで、「かんぽ生命に入っていてよかった」と感動いただけるよう取り組みます。また、その体験価値をご評価いただいたお客さまから、そのご家族や知人、さらには地域・社会全体へかんぽ生命をお勧めいただくことで、お客さまを広げてまいります。
具体的には、「お客さま一人ひとりに寄り添う適切なご提案」、「その場で完結する簡便な手続きの提供」、「チーム一体でのきめ細やかなサポート」、「お客さまとのつながりを重視したアフターフォローの充実」に取り組んでまいります。
a.お客さま一人ひとりに寄り添う適切なご提案
お客さまのニーズや必要な保障内容などについてデジタルを活用したツールにより可視化するとともに、遠方にお住いのご家族等にも同席いただけるシステムを導入し、お客さま一人ひとりに寄り添う適切なご提案を実現してまいります。
b.その場で完結する簡便な手続きの提供
デジタル技術の活用により、お客さまのニーズに応じて、オンライン、対面等様々なお申込み・ご請求形態を選択できるようにしてまいります。2022年度より、お客さま自身のスマートフォン等の端末から被保険者同意及び告知を可能とするため、アジャイル開発※手法を用い、一部地域から段階的に試行実施してまいります。このほか、インターネット上での入院・手術保険金請求の拡大等に取り組むとともに、マイページからの入院・手術保険金請求に対して、専門スタッフ(カスタマーセンター)がリアルタイムにサポートするチャット機能を実装する等、その場での諸手続き等の完了を可能にしてまいります。
※ アジャイル開発とは、システムを開発する手法の一つです。短期間に設計やテストを繰り返しながら開発を進めることで、サービス開始までの開発期間を短縮するとともに、開発途中の仕様・要件変更にも柔軟に対応することを目指します。
c.チーム一体でのきめ細やかなサポート
お客さまのご契約情報やお問合せ情報等をお客さま単位で集約した、お客さまデータベースを構築し、コンサルタント、郵便局窓口、専門スタッフなど、お客さまにご対応するすべての社員がチーム一体で、きめ細やかなあたたかみのあるサポートを提供できる環境を整備してまいります。2022年度より、一部地域において、試行的に新契約申込時にお客さま、コンサルタント及び専門スタッフをオンラインで繋ぎ、お客さまのご意向確認、サポート体制のご案内、ご不明点の解消等を実施してまいります。
d.お客さまとのつながりを重視したアフターフォローの充実
訪問による対面対応に加えて、オンライン会議など様々な方法による手厚いアフターフォローや、メール・SNS等によるお客さまごとに最適なタイミングでのアフターフォローを行い、お客さまのニーズに幅広くお応えし、お客さまの周囲の方々も含めた信頼の獲得を目指してまいります。具体的には、マイページ会員のうち満期を迎えるなど所定の要件を満たすお客さまへメールを順次配信し、動画で節目を迎えたことをお祝いするとともに、各種手続きや次のステージのライフプランのご相談をサポートする取り組み等を行うことで、手厚いアフターフォロー等を実施してまいります。
当社は各種取組の成果を測定するため、1年に一度実施しているお客さま満足度調査に加え、リアルタイム調査の導入を進めております。リアルタイム調査では新規加入、保全手続き及び保険金請求など、お客さまとの重要な接点ごとにお客さまのご体験に関するご評価や「お客さまの声」を能動的に取得することで、サービス改善に繋げるPDCAサイクルの高速化を実現してまいります。また、2022年度には、アンケートシステム(クラウドサービス)からのSMS配信により、よりタイムリーにご評価や「お客さまの声」を取得する取り組みを開始してまいります。
イ.ESG経営の推進(社会課題の解決への貢献)
当社は、自らの社会的使命を果たすことで、サステナビリティ(持続可能性)を巡る社会課題の解決に貢献してまいります。
当社が優先的に取り組む社会課題(マテリアリティ)として、「郵便局ネットワーク等を通じた保険サービスの提供」、「地域と社会の発展・環境保護への貢献」、「健康増進等による健康寿命の延伸・Well-being※1向上」、「社員一人ひとりが生き生きと活躍できる環境の確立」、「社会的使命を支えるコーポレートガバナンス」の5つの課題を設定し、解決に向けて取り組んでまいります。
具体的には、カーボンニュートラルの実現に向けた温室効果ガス排出量の削減や女性管理者比率など具体的な目標を設定するとともに、TCFD※2提言に沿った、気候関連のリスク管理や低炭素経済への移行計画の検討等に取り組んでおります。今後も推進態勢のさらなる強化を図るとともに、サステナビリティレポートや当社Webサイト等を通じて、積極的に情報開示をしてまいります。
加えて、お客さまが抱える多様なお悩みにお応えし、お客さまの生活に寄り添うサービスを提供することで、少子高齢化等の社会課題の解決や健康寿命の延伸に貢献するとともに、当社をより身近に感じていただき、さらなる信頼を構築してまいりたいと考えております。具体的には、2022年4月に、企画・検討態勢強化を目的として経営企画部みらいデザイン室を新設するとともに、広く社内からアイデアを募集する施策として社内ベンチャー制度「Kampo TSUNAGU Challenge!」を開始しました。同時に社外からアイデアを募集する取り組みとして、アフラック生命保険株式会社(以下「アフラック」といいます。)と共同で「かんぽ生命 - アフラック Acceleration Program」を実施しております。スタートアップのサービス・技術と、かんぽ生命・アフラック両社の経営資源を掛け合わせた協業の実現を目指しており、協業を通じて、お客さまへの提供価値向上の実現に努めてまいります。
※1 Well-beingとは、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが満たされた状態にあることです。
※2 TCFDとは、「気候関連財務情報開示タスクフォース(Task Force on Climate-related Financial Disclosures)」の略語です。
③ 再生と成長のための土台作り
ア.企業風土改革・働き方改革
当社は、経営陣と社員が将来のビジョンを共有し、一人ひとりがやりがい(ES)を感じながら会社とともに成長する企業を目指します。
具体的には、経営陣と社員のコミュニケーションの活性化、中長期的な人材ポートフォリオモデルを踏まえた社員一人ひとりの多様なキャリア形成の支援、マネジメント力の強化、人事評価制度の高度化を柱とした企業風土改革を推進してまいります。また、全社員を対象としたES調査(社員満足度調査)を通じて、上記取り組みの効果検証及び改善、並びに全社及び各職場の課題解決に全社を挙げて取り組むとともに、テレワークの活用などにより多様で柔軟な働き方を選択できる環境を整備し、働き方改革を推進してまいります。併せて、女性活躍推進、仕事と育児・介護との両立支援、障がい者雇用の推進、性の多様性に対する理解浸透等による、ダイバーシティの実現を推進してまいります。日本郵便株式会社から当社に出向したコンサルタント等を含めてこれらを推進し、かんぽ生命社員としての使命感や一体感及び自らの成長を通じたやりがいやモチベーションの着実な醸成に繋げてまいります。
2022年度には、次世代リーダー育成プログラムを策定し、時代の変化に柔軟かつ迅速に対応し組織を牽引するマネジメント層を計画的かつ戦略的に育成するとともに、タレントマネジメントシステムにおいて、個々の社員のスキルや社員対話(キャリア面談)を踏まえた育成方針などを一元管理・見える化する機能を実装することで、社員一人ひとりに寄りそった育成・マネジメントの実現に向けて取り組んでまいります。
これらの取り組みにより、社内コミュニケーションが活性化され、相互理解の下、全社が一体感を持ち、お客さま本位の考え方に基づき自律的・主体的に行動する会社を実現してまいります。
イ.ガバナンスの強化
当社は、組織としての透明性・公平性を確実に高め、さらには、社員一人ひとりのリスク感度を高めることにより、健全な事業運営を行ってまいります。
健全なコーポレートガバナンスを確保した上で、マネー・ローンダリング並びに犯罪防止等対策及び個人情報保護・情報セキュリティ対策を強化するなど、健全な業務運営を確保するための取り組みを継続して実施してまいります。具体的には、当社の保険サービスのご提供などが、マネー・ローンダリング等に悪用されることを防止する観点から、事業の特性及び代理店の状況並びに法令等を踏まえたリスクの特定・評価の見直し、顧客管理態勢の高度化に取り組んでおります。不適切な取扱いが発覚した場合には、速やかに事実確認を行うとともに、再発防止策を講じ、その徹底を図ってまいります。このほか、DX戦略の推進に伴い、サイバー攻撃への検知をはじめシステムリスク管理の強化に取り組んでまいります。
上記の中期経営計画の取り組み等を実施することで、株主、投資家をはじめとする様々なステークホルダーの皆さまのご期待に沿えるよう、持続的な企業価値の向上を目指してまいります。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有(被保有分)を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。